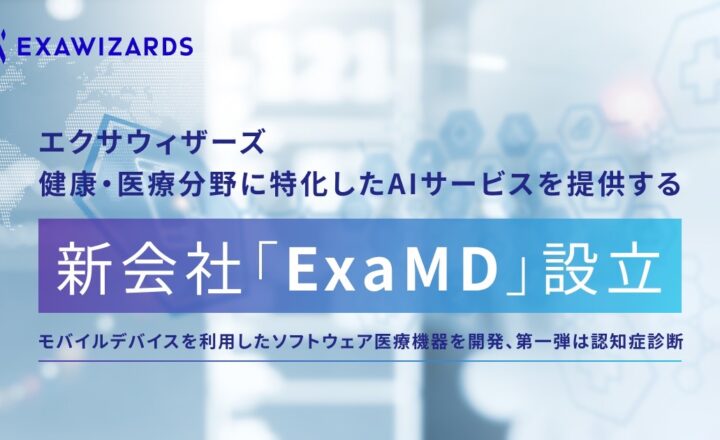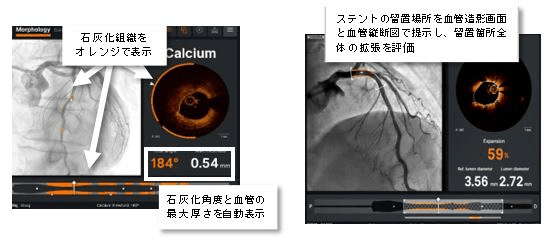頭痛治療用アプリや頭痛AI診断機器の開発、企業向けの健康管理サービスの提供を行う株式会社ヘッジホッグ・メドテック(本社:東京都文京区、代表取締役 CEO:川田裕美、以下ヘッジホッグ・メドテック )の龍野薫が日本における一次性頭痛の診断の遅れとその診断が数年間で変遷することについてまとめた論文を発表し、Springer Nature の一部門である国際学術誌 Cureusに掲載されました。

一次性頭痛を早期に正確な診断することは、患者の生活の質を向上させ、鎮痛薬の使い過ぎを防ぐために不可欠です。適切な診断が行われない場合、患者の生活の質が低下するだけでなく、他の医療機関への再受診や重複検査が生じ、医療費の増加など医療システム全体に悪影響を及ぼす可能性があります。日本では一次性頭痛の有病率は高いものの、頭痛の誤診や過小診断に関する研究は限られています。本研究では、一次性頭痛の診断の現在の傾向を明らかにし、初診から5年間にわたる診断の変化を検討することを目的としています。
2010年7月から2024年11月の期間における日本の健康保険レセプトデータベースを用い、対象は18歳以上の外来受診患者としました。各頭痛診断カテゴリーはICD-10診断コードに基づいて①片頭痛及び薬剤の使用過多による頭痛(MOH)、②緊張型頭痛(TTH)、③三叉神経・自律神経性頭痛(TACs)、④その他の一次性頭痛、⑤その他の頭痛(二次性頭痛を含む)、明確な診断がつかない場合は「未確定」と分類しました。初診から3か月、6か月、12か月、36か月、60か月後の診断を初診時と比較して評価を行いました。
合計336,596名の患者データを解析し、平均年齢(標準偏差)は40.2歳(12.3)、男性は91,830名(27.3%)、女性は244,766名(72.7%)でした。初診時の診断で未確定が28.5%、片頭痛・MOHが54.0%、TTHが16.7%、TACsが0.3%、その他の一次性頭痛が0.5%、その他の頭痛が0.1%でした。初回受診から3~5年後に確定診断を受けていたのは86,164名(26.0%)でした(3~5年後に診断が記録されなかった患者を除く)。そのうち51,360名(59.6%)は初診と同じ診断でした。3~5年後の確定診断は、片頭痛・MOHが78.8%、TTHでが20.2%、TACが0.4%でした。最も多い初診の診断からの変更パターンは、初診でTTHから片頭痛・MOHへの変更でした。(2,522人の2.9%)
本研究から、患者の4人に1人以上が初診時に確定診断を受けておらず、40%を超える患者が後に初診と異なる診断結果を受けていたことがわかります。特に初診時にTTHと診断された患者の診断が、片頭痛の診断に変化することが多く確認されました。これは片頭痛が過少診断されやすいということを示しており、日本の医療において、正確な頭痛診断がなされるまでに依然として遅れと困難があることを示しています。
今後の展望
患者が適切な治療を受けられるよう、頭痛診断を迅速にかつ正確にしていく必要があります。このためにはプライマリケア医への一次性頭痛に関する教育の強化、標準化された診断ツールの活用促進そして人工知能などの臨床意思決定支援システムの導入が期待されます。株式会社ヘッジホッグ・メドテックでは頭痛AI診断ツールの開発を進め、一次性頭痛の診断精度の向上を実現し、正確な診断までの手間や難しさが軽減されることを目指すとしています。